ルターの自由
ルター(Martin Luther, 1483~1546)は、ドイツの宗教改革者です。
『キリスト者の自由』では、キリスト者は自由な主人であり誰にも従属しないということと、キリスト者は奉仕する僕であって誰にでも従属しているということが、二つの原則として同時に示されています。この矛盾すると思われる二つの原則が、キリスト者においては両立すると考えられているのです。
ルターは、次のように述べています。
われわれは、キリスト者は信仰で十分であり、義とされるために何の行ないも必要としなければ、たしかにすべての戒めと掟とから解放されてもいる。彼が解放されているなら、たしかに自由であるのだ。これがキリスト者の自由であり、唯一の信仰である。
キリスト教における自由意志の問題
キリスト教における自由意志の問題に触れたとき、日本人なら疑問を抱きます。「意志は意志」なのであり、「意志は、自由意志である」というように、意志に「自由」を付け加えることに違和感を覚えるからです。
『古今和歌集』の[仮名序]には、「やまとうたは、人のこころをたねとして、よろづのことのはとぞなれりける」とあります。心とは、生まれることで世界が芽生え、死ぬことで世界が枯れ果てるものを、世界にたくさん居ることにする、生活世界のために必要な考え方なのです。
日本人の世界観においては、制限の不在を意味する自由を用いて、「意志」を「自由意志」と表現することに違和感を覚えます。日本人が世界を観るとき、意志は、(制限の不在を意味する)自由であるか自由でないかという問題の場にはないからです。
世界観の前提として、キリスト教のように全知全能の絶対者を設定した場合に、意志は自由であるか否かが問題となります。日本人のように、絶対や究極を設定しない、もしくは想定に留めておくならば、意志は自由である否かという問題は発生しなくなります。
例えば、人間が人形を操るとき、人間には意志があり、人形には意志がないと感じられます。この内在の原理を、超越の設定により、階層をずらして「人間→人形」の関係を「神→人間」の関係へと移行させます。そうすると、自分は人形ではないと言い張る必要が出てくるというわけです。
この問題に対して日本思想の中に類例を探すと、江戸後期の儒学者である佐藤一斎(1772~1859)の思想を挙げることができます。彼の『言志四録』には、次のような文章が出てきます。
人の富貴貧賤、死生寿殀、利害栄辱、聚散離合に至るまで、一定の数に非ざるは莫し。殊に未だ之を前知せざるのみ。譬えば、猶お傀儡の戯の機関已に具われども、而も観る者知らざるがごときなり。
人の貧富・死生・寿命・利害・名誉・縁などの運命は、既に定まっているという考え方が示されています。ただ人間は、その運命を知らないだけだというのです。そのことが、あやつり人形の芝居に例えられています。あやつり人形のからくりは定まっていますが、観客はそれと知らずに見ているようなものだというのです。
キリスト教においては、この人間とあやつり人形の関係が、全知全能の神と人間という関係に階層をずらした形で現れます。そのため、キリスト教において人間の自由意志の問題が発生し、意志は、自由な意志であることが必要になり、それの肯定が要請されることになるのです。
※第21回「近代を超克する(21)対リベラリズム[4]ホッブズとロックとルソー」はコチラ
※本連載の一覧はコチラをご覧ください。
2
コメント
この記事へのトラックバックはありません。







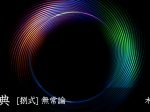



















この記事へのコメントはありません。