『日本式自由論』第二章 鎌倉時代
- 2017/2/9
- 思想, 文化, 歴史
- feature8
- 2,340 comments

第二章 鎌倉時代
本章では、鎌倉時代の文献に現れる自由を見ていきます。
第一節 御成敗式目
鎌倉幕府の基本法典である『御成敗式目(1232)』には、自由の用例が数多く示されています。
[四条]では〈理不尽の沙汰甚だ自由の姦謀なり〉とあります。ここでの自由は、謂れのないという否定的な意味です。[第三十七条]では〈しかるに近年より以降、自由の望みを企て〉とあります。ここでの自由は、我儘勝手に所有欲を充たすということで否定的なものです。[第四十条]では〈猥りに自由の昇進を求むる〉とあります。我侭勝手な自由であり非難の意味で使われています。
[御成敗式目追加]においても、多くの自由が示されています。〈而して地頭等自由のままに相論の条、慥かに停止さるべし〉、〈左右無く出家せしめ、なほ所領を知行する事、甚だ自由の所行なり〉、〈禁忌を称して自由に帰国の条〉、〈自由の対捍(不服従・抵抗)を致し〉、〈自由に任せて上洛遠行あるべからず〉、〈今更自由の新儀を致すべからず〉、〈領家預所の免許を蒙らずして、自由に任せ立用に任せ及ばず〉、〈或いは自由に洛中に横行の由あまねくその聞えあり〉などが挙げられます,
また、[建武以来追加]においても、〈近年禁制に背き、自由の競望を致すか〉、〈自由の横領を致すの由その聞えあり〉、〈その外の自由の新関は厳密に停廃すべきの由、仰せ下されうべきか〉、〈左右無く庭中を企つるの条自由の至りなり〉、〈洛中辺土ならびに田舎に居住せしむる云々、自由の至りなり〉などが挙げられます。
『御成敗式目』は、道理という規範が基と成っています。如何に強大な権力者といえども、自らの自由によって振舞うことは禁止されているのです。『御成敗式目』では、道理に由ることを善しとし、道理に由らない行為を「自由」としています。〈ただ道理の推すところ、心中の存知、傍輩を憚らず、権門を恐れず、詞を出すべきなり〉とあり、道理によって言葉を発すべきことが述べられています。そこでは、他人の目や権力よりも道理が優先されるべきことが明記されています。よって、道理に由らない自由は、否定的な意味として使われているのです。
第二節 吾妻鏡
鎌倉時代の歴史書である『吾妻鏡』は、治承4年(1180)源頼政の挙兵から、文永3年(1266)までの87年間を変体漢文の日記体で記しています。『吾妻鏡』の中には、〈恣に私威を耀かし、自由の下知を成して〉、〈定めて自由の沙汰に似候か〉、〈由緒無く自由の押領に任するの由〉、〈自由の押領〉、〈自由の任官〉、〈自由の狼藉〉、〈自由の張行〉、などの用法が見られます。これらの自由も六国史における自由と同様に、「ほしきまま」としての放縦であり、糾弾対象となっています。特定の権威に対立した、悪しきことに基づいて行う行動が自由として捉えられているため、否定されるのです。
また、〈自専の慮を挿み〉や〈動もすれば自専の計有り〉などのように「自専」という言葉も用いられています。自主独立・独断専行といった意味で「自専」が用いられているようです。
第三節 鎌倉文化
鎌倉文化における自由として、狛近真による雅楽書『教訓抄』(1233)を挙げることができます。例えば、〈是偏ニ名利ノ罪、自由ノ科ノガレガタキユヘ也〉とあります。財物を貪ることは、自由の一つであり、悪しきこととされています。また、〈自由ノ案立〉は、習も説もなく我説を立てることを言い、〈自由ノ今案〉で、説もなく習もない自分勝手な演奏法を指しています。
鎌倉中期の説話集である『十訓抄(1252)』には、〈あるいは自由のかたにておだやかならず。これ、わが涯分をはからず、さしもなき身を高く思ひ上げて、主をも軽め、傍人をも下ぐるなり〉とあります。この自由は、身の程を弁えずに思い上がることであり、否定的なものです。
無住(1226~1312)の仏教説話集『沙石集(1283)』には、〈賢遁の門に入りて、僅かに寒を防ぎ、飢ゑを休めて、心安く身自在にして、一生を送らんと思ふ、まめやかに賢き心なり〉とあります。ここでの自在は、心が安らかな上での身の自在であり、肯定的な意味です。また、〈楽天云はく、「富貴にして苦あり。苦は心の危く愁ふるにあり。貧賤にしても楽あり。楽は身の自由に有り」と云へり〉とあります。貧しいから楽なこともあり、身体的に楽が出来ることが身体の自由として述べられています。また、〈自由ノ邪推〉という記述もあり、この自由は放埓なわがままです。
吉田兼好の随筆『徒然草(1330~31)』の第六十段には、〈この僧都、みめよく、力強く、大食にて、能書・学匠・弁説、人にすぐれて、宗の法灯なれば、寺中にも重く思はれたりけれども、世を軽く思ひたる曲者にて、よろづ自由にして、大方、人に従ふといふ事なし〉とあります。他人を気にせず、自らに由って行動している人に対して言及されています。
第四節 鎌倉仏教
鎌倉仏教においても、自由が数多く論じられています。
法然(1133~1212)の『選択本願念仏集』には、源信の『往生要集』と同じく『西方要決釈疑通規』からの引用で、〈久しく生死に沈んで制すること自由ならず〉とあります。生死に執着してしまうと、自己を制することができないというのです。
また、『七箇条制誡』では、〈黒闇の類、己が才を顕はさむと欲し、浄土の教えをもつて芸能として、名利を貪り檀越を望み、ほしいままに自由の妄説をなして、世間の人を誑惑す〉とあります。ここでの自由は、妄説で他人をたぶらかすのですから否定的な意味を持っています。ちなみに、〈黒闇の類〉は正しい行ないをせぬ者のことです。〈芸能として〉とは、和讃とか礼讃にふしをつけてとなえるのを指すとされています。〈檀越〉は、相に衣食などを施す供養主で、施主・檀那とも言います。〈誑惑〉とは、たぶらかしまどわすということです。
親鸞(1173~1262)の『教行信証』には、自在が語られています。〈諸仏の大法を念ぜば、略して諸仏の四十不共法を説かむと。一つには自在の飛行意に随ふ、二つには自在の変化辺なし、三つには自在の所聞無?なり、四つには自在に無量種門を以て一切衆生の心を知ろしめすと〉とあります。四十不共法とは、仏だけがもっている勝れた四十種の特質です。そのうちのいくつかが自在として語られています。ちなみに、無?は無礙と同じ意味で、さわりのないことです。また、〈豪貴富楽自在なることありといへども、ことごとく生老病死を勉(まぬか)るることを得ず〉とあります。自分に富や楽があるからといっても、その自分は生老病死の四苦を逃れることができないと語られています。ここでの自在の「自」に掛かるものは、富や楽などのため、ここでの自在の評価は低いものとなっています。
親鸞の『末燈抄』の[自然法爾の事]では、〈自然といふは、自はおのづからといふ。行者のはからひにあらず。然といふは、しからしむといふことばなり。しからしむといふは行者のはからひにあらず、如来のちかひにてあるがゆゑに法爾といふ。法爾といふは、この如来の御ちかひなるがゆゑに、しからしむるを法爾といふ〉とあります。自然法爾とは、自己の力で仏になろうとしたり、善行を積んで仏に救われようとしたりする人為をすて、ひたすら仏の願力のままに身をゆだねることです。親鸞の弟子にの唯円による『歎異抄』には、〈わがはからはざるを自然とまうすなり。これすなはち他力にまします〉とあります。
中世において「自然」には「ジネン」と「シゼン」という二つの訓み方がありました。「ひとりでに」や「おのずから」を意味する場合には「ジネン」とよまれ、「もしも」や「万一」を意味する場合には「シゼン」と読まれていました。
道元(1200~1253)の『正法眼蔵』の[仏性]では、〈百丈山大智禅師、衆ニ示シテ云ク〉とし、禅師の言葉を引用して自由の語が出てきます。〈於後能く因果を使得す、福智自由なり〉や〈五陰に礙へられず、去住自由にして、出入り無難なり〉とあります。福智とは、菩薩の善を行なって徳を積む福行と、自己の悟りを完成するための智行のことです。その福智が自らに由るのですから、肯定的な意味です。また去来自由とは、ある環境において出入りが可能であるという意味です。
[阿羅漢]には、〈諸の漏を已に尽し、また煩悩無く、己の利を逮得し、諸の有結を尽して、心は自在を得たり〉とあります。煩悩がない状態になれば己の利はついてきて、諸々の煩悩の束縛が解けてしまへば心は自在を得るというのです。また、〈心得自在の形段、これを高処自高平、低処自低平と参究す。このゆゑに、墻壁瓦礫あり。自在といふは、心也全機現なり〉ともあります。心は自在なることを得たということは、高処にあれば高処にあって平らかに、低処にあれば低処にあって平らかなことです。だから、高処には墻壁(隔てるもの)があり、低処には瓦礫があるのです。心の自在というのは、心のすべてのはたらきが自由に現れることだと示されています。
[唯仏与仏]には、〈得道のあしたより、涅槃のゆふべにいたるまで、一字をもとかざりけるとも、とかるることばの自在なりける〉とあります。仏が悟りを開いて涅槃に入られるまで、生涯一字も説かなかったといいますが、その後に説かれた言葉は自由自在であったというのです。
明恵(1173~1232)の『梅尾明恵上人遺訓』には、〈先づ身心を道の中に入れて、恣(ほしいまま)に睡眠せず、引くままに任せて雑念をも起さず、自由なるに随ひて坐相をも乱らず〉とあります。ここでは精神な自由が環境へ対応するための自由に繋がっており、肯定的に用いられています。自由になるにつれ、自らに由るにつれて、坐相(坐禅の姿勢)は乱れなくなるということです。『鎌倉遺文』では、〈若(も)し数日京に住(とど)まる要事有らば、或いは同法或いは侍者・下僧等・一身に相具すること自由なるべからず〉とあります。規則違反をするなという意味で用いられています。誰でも良いから必ず同行者を連れて行け、単身で出京してはならぬ、その点を自由に考へてはならぬという意味です。
第五節 軍記物語
『長門本・平家物語(1177~84)』では、〈自由に任せて延暦寺の額を興福寺の上に打せぬるこそ安からね〉とあります。ここでの自由は、共同体における乱暴狼藉を意味しています。その乱暴狼藉を咎めています。
鎌倉中期から後期の作である『源平盛衰記』では、〈自由の京(きょう)上(のぼり)も其(それ)恐(おそれ)ありと存(ぞんじ)〉とあります。勝手に京都に向かうことが憚られたことが語られています。ここでの自由は勝手な判断という意味で、否定的な意味合いを持っています。
※本連載の一覧はコチラをご覧ください。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。






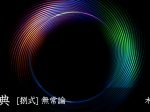




















この記事へのコメントはありません。