解説
今回から『夢幻典』をはじめます。本作は、以前に連載していました『聖魔書』の姉妹編に位置づけられます。
『聖魔書』はユダヤ・キリスト教の『聖書』における構造を意識していました。一方、この『夢幻典』は東洋哲学、特にインド哲学の構造を意識しています。はじめは、仏教の構造を対象としていたため、『夢幻経』という題名にしようかと考えていました、「経」は仏の教えという意味がありますから。
ただ、仏教の誕生前にはウェーダという宗教文書によるインド哲学の長い伝統があり、それらを踏まえて総合的に書かなければ仏教の意図したところは分からないだろうと思えてきたのです。そのため、この書は『夢幻経』ではなく、『夢幻典』という題名になります。
まず、ここの『無言論』では、“言葉が有ること”に対する“言葉が無いこと”についての問題が取り上げられています。この問題は特殊であり、“言葉の無さ”を言葉によって語り示すというアクロバティックな言論が為されることになります。無理なことを、無理矢理に語るという無理難題です(笑)。
ここで参照すべき一つの考え方は、『聖書』の思想にあります。特に『ヨハネによる黙示録』(新共同訳)では、次のような有名な文章からはじまっています。
初めに言(ことば)があった。言は神と共にあった。言は神であった。この言は、初めに神と共にあった。万物は言によって成った。成ったもので、言によらずに成ったものは何一つなかった。言の内に命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。
ここには欺瞞があります。その欺瞞を、インド哲学の洞察を参照しながら、ここで反駁を試みています。つまり、キリスト教的な観点から言えば、光に対する“暗闇”を語る営みがここでは展開されているのです。それはキリスト教的な観点からは、まさしく邪悪な営みに見えてしまうものなのです。
“言葉の無さ”を語るということは、学問的に言えば、言語論的な視点と存在論的な視点から示すことができるでしょう。この二つの視点は、集団からの視点と個人からの視点という類推で理解することもできるでしょう。そして個人からの視点は、“各個人”と“自己”という概念分析からさらに分割して論じることができるでしょう。
この“言葉の無さ”を語るという無理を通した上で、今後は言葉による実践が示されることになります。
※本連載の一覧はコチラをご覧ください。
2
コメント
この記事へのトラックバックはありません。







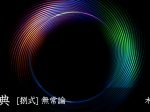





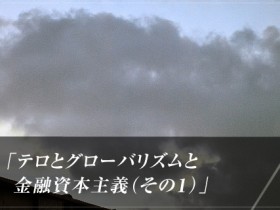












この記事へのコメントはありません。