ユネスコ記憶遺産とは精神のグローバリズムである
- 2015/10/29
- 文化, 歴史
- 2,332 comments
ある歴史を共有できる範囲は、自生的な共同体の範囲を超えないと書きましたが、そもそも歴史とは何でしょうか。それはそれを聞いた誰もが深い心情的なレベルから納得できる「物語」のことです。英語history、ドイツ語Geschichteにもそういうニュアンスがもともと込められていますし、フランス語histoireに至っては、初めから両方の意味に解せられます。ですから、神話と物語と歴史とは本来別ものではなく、特定地域に根差したひとつながりの連続性を持っているのです。
かつて小林秀雄はこう書きました。
母親の愛情が、何も彼もの元なのだ。死んだ子供を、今もなお愛しているからこそ、子供が死んだという事実が在るのだ、と言えましょう。愛しているからこそ、死んだという事実が、退引きならぬ確実なものとなるのであって、死んだ原因を、精しく数え上げたところで、動かし難い子供の面影が、心中に蘇るわけではない。
(『歴史と文学』)
死なしたくない子供に死なれたからこそ、母親の心に子供の死の必然な事がこたえるのではないですか。僕等の望む自由や偶然が、打ち砕かれる処に、そこの処だけに、僕等は歴史の必然を経験するのである。僕等が抵抗するから、歴史の必然は現われる。僕等は決して抵抗を止めない、だから歴史は必然たる事を止めないのであります。
(同前)
ここには、「事実」とか「歴史」とかいう言葉で私たちが通常理解している概念の、鮮やかな転倒が見られます。客観主義から実存主義へと、歴史観を大きくひっくり返しているのです。
事実や歴史がまずあるからあなたの愛や思いが生まれるのではない。あなたの愛や思いこそが事実を事実たらしめ、歴史を歴史(物語)として紡ぐのである、そう小林は説いています。歴史が生活の共有を通して得られる共通の思いをけっして超えることができず、したがってそれが成り立つ範囲は、せいぜい自生的な共同体までがぎりぎりであるという命題がここから導かれるでしょう。
私たちは、歴史認識のグローバルな共有などという安易な理念に跪拝してはならないのです。そのような理念は、むしろ一人の個人の、愛し合い憎しみ合った私たち二人の、そうして心情を共有しあった小さな仲間たちの大切な生の記憶を大きな声によって蹂躙していくのです。でも私たちは「決して抵抗を止めない」。それこそが、中共政府のデタラメやそれを安々と追認してしまうユネスコ事業の(おそらくは作為された)いい加減さに対して反対の声を上げる思想的な根拠と言えましょう。
最後にもう一度言います。敵は中共政府にだけあるのではなく、その中核はむしろ「記憶遺産」という精神のグローバリズムにこそあるのです。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。













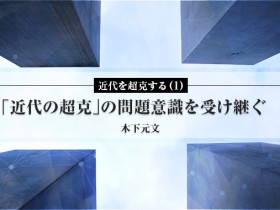












この記事へのコメントはありません。