≪木下元文の読書感想文≫ 中野剛志『富国と強兵 地政経済学序説』
- 2016/12/15
- 思想, 歴史
- 457 comments

今回は、評論家・中野剛志さんの『富国と強兵 地政経済学序説』を読んだ感想について書いてみます。
目次
地政経済学とは?
本著は、およそ25年におよぶ著者の探究の結果たどりついた「地政経済学」について書かれたものです。それは、「富国」と「強兵」の相互依存的な関係を解明する理論であり、地政学と経済学を総合した思考様式として提示されています。
紙の本の長さは525ページもあり、まさに大著です。細かいところにまで言及していくとキリがないので、特に素晴らしいと思った箇所と気になった箇所について3点ほどピックアップして述べてみることにします。
素晴らしいと思った1点目:主流派経済学への批判
素晴らしいと思った点として、まずは第1章から第3章にかけての主流経済学への批判とその代替案が挙げられます。信用貨幣の説明から、ポスト・ケインズ派の「内生的貨幣供給理論」などを参照し、機能的財政の有用性を説く論理には説得力があります。特に「最後の貸し手」としての中央銀行および「最後の雇い手」としての政府の役割については、重要な概念だと思われます。
最初から密度の高い議論が展開されており、著者によって分かりやすいよう丁寧な説明が行われています。ですが、それでも経済用語の基礎知識がないと読むのが少しつらいかもしれません。
素晴らしいと思った2点目:社会関係を把握する方法
第13章には、経済学者コモンズの意見を参照し、部分と全体の有機的な関係を把握する方法についての論述があります。コモンズは、部分と全体の有機的な関係を構築しようとするホワイトヘッドの「有機体的機械論」の趣旨自体は受け入れながらも、それを深めた見解を提示するにいたっています。
機械の中にも、部分と全体の有機的な関係は確かにある。しかし、それは、新陳代謝や生死といった現象がある生命体における有機的な関係とは異なるものである。さらに、社会における有機的な関係である「ゴーイング・コンサーン」もまた、機械や生命体とは異なっている。したがって、部分と全体の有機的な関係を把握する方法は、物理的な「機械論」と、生命体の「有機体論」そして社会制度論としての「ゴーイング・コンサーン」の三つに分けなければならない。
ここでの「ゴーイング・コンサーン」は、簡単に言うと取引行為の総体を意味しています。この考え方は、保守主義における欠陥を克服する観点になりえます。
アンソニー・クイントンの『不完全性の政治学』には、伝統主義・有機体主義・政治的懐疑主義という保守主義の三つの特殊原理が挙げられています。有機体主義の原理とは、社会は一体として自然に成長するものであり、組織された生きた全体であって機械的な寄せ集めではない、という社会観です。この社会観は、機械的なそれよりはマシですが、かなりの欠陥品です。なぜなら社会とは、一つの有機体ではなく、有機体である人間の集まりだからです。
人間は、人々の関わり合いによって一つの有機体としての社会を形成するのではありません。人の間において人間は、一人の人間として、他の人間と互いに関係を築いていくのです。ですからそこには、機械論と有機体論だけでは語れない領域があるのです。その領域を埋めうる現実的な観点として、コモンズの考えは傾聴に値します。
素晴らしいと思った3点目:富国と強兵の関係性
「富国」と「強兵」は密接不可分なものとして、本書ではそれらの関係の重要性が強調されています。戦後日本では、強兵なき富国の追求がありましたが、それは冷戦という特異な国際環境が可能にしていたというのです。そのため冷戦後の日本人に対し、〈「強兵」を放棄した国民には「富国」など望むべくもないという教訓〉が提示されることになるのです。
その上で本書では、絶望的な未来も、かすかな希望の可能性も示されています。
あるいは日本において、東アジアの地政学的危機によって覚醒した新たな世代が登場し、親米路線と新自由主義から決別して、二一世紀の富国強兵を実現するという可能性はまったくあり得ないとは、誰にも断言できまい。
いずれにせよ、日本がどのような運命をたどるのかは、それほど遠くない将来に判明するであろう。
少なくとも、本書には希望を抱きうるための理論が提示されています。それは、やはり偉大な仕事なのだと思われます。
気になった1点目:地政学的な観点からの起源の主張
本書でもっとも違和感を覚えたのは第7章になります。この章では、資本主義がなぜ西ヨーロッパから始まったのか、産業革命がなぜ最初にイギリスで起きたかについて、地政経済学的な意識から問われています。
さまざまな理論家の意見や歴史状況を踏まえた後に、著者は〈西ヨーロッパは、その内外における地政学的な環境の特異性のおかげで、イスラム世界や東洋世界に先んじて資本主義を成立させることに成功したのだと解釈することができる〉と述べています。第8章の冒頭では、〈産業革命の起源は、端的に地政経済学的なものであった〉という記述があります。
ここのあたりは、正直どうとでも言えてしまえる問題ではないでしょうか。すでに起こってしまった事象に対し、地理的・政治的・経済的な状況をそれらしく後付けし、始めての根拠をでっちあげるやり方はかなり疑わしいと言わざるをえません。なぜなら社会的な観念に対し、それが発生した理由は検証可能でしょうが、それが始めて発生した理由は検証がほとんど不可能だからです。なぜ不可能かというと、始めてという状況、つまり、その概念を知らなかった社会状態を作り出すことが困難だからです。
私にとってこの第7章の論述は、「地政経済学」という新しい概念を補足するための勇み足に感じられてしまいます。資本主義が西ヨーロッパから始まった要因の一つに、地政学的な環境の特異性を指摘することはもちろん可能です。しかし、西ヨーロッパから始まったことの論証は無理だと思われますし、第7章に書かれている内容を読んでみても納得できませんでした。
そもそも序章では、地政学の開祖マッキンダーによる地理学の見解として、〈真理の一側面に触れることができるに過ぎない〉という考えが紹介されています。第7章では、マッキンダー的な謙虚さが抜け落ちてしまっているようです。
もう少し論じるなら、資本主義という言葉の定義もかなりいい加減だと感じられました。例えば第13章では、〈資本主義とは、信用貨幣を基礎とする経済〉という言い方がなされています。この定義では、資本主義が西ヨーロッパから始まったとはとても言えなくなってしまうでしょう。
気になった2点目:有効需要の不足に対する対策の効果
気になった点としては、12章におけるケインズとデューイの提言について論じている箇所も挙げられます。
もっとも、『一般理論』は一九三六年に刊行されているから、一九三九年の段階でデューイが『一般理論』を読んでいたとしても不思議ではない。いずれにしても、デューイは、ケインズ同様、有効需要の不足というデフレ不況の特異な性格を正確に把握していたのである。ただし、その対策として、ケインズが需要刺激を主張したのに対し、デューイは生産能力の制限を提言しているという違いはある。とは言え、需要不足とはすなわち供給過剰なのであるから、対策の効果としては同じであると言ってよい。
細かいところではありますが、「需要刺激」と「生産能力の制限」では、対策の効果は同じではありません。両方とも有効需要の不足に対する対策ではありますが、どちらをどれだけ採用すべきであるかは、そのときの状況に依存します。なぜなら、それぞれの対策の効果には差があるからです。その社会が保有する供給能力がどれだけであるべきかによって、両者の政策を使い分ける必要があるからです。
気になった3点目:テロリズムの脅威と国内分裂
第16章には、国際的なテロリズムの脅威について言及があります。国際政治学者のスティーブン・ウォルトを参照し、テロリズムの脅威が国民の連帯を高めるのではなく、逆の結果をもたらすという考え方が示されています。
テロリズムは見えにくい脅威であり、国内にテロリストが潜んでいるという恐怖をかきたてる。このため、国民は国外ではなく国内に不安を感じ、隣人を信じることができなくなる。こうして、テロリズムは国内社会を分裂させる方向へと働くのである。
この見解は、さすがに安易だと思われます。テロリズムは、その規模や思想や状況によって、国民の連帯を強めることも、国内社会を分裂させることもありえます。そのときの政治家の決断によって、国内の安定性は左右されることになります。
テロリズムは恐怖によって、ある社会の秩序を揺さぶります。ですから、その秩序に属する人間たちは、テロリズムへ対抗するために団結しようとするでしょう。ここで重要なポイントは、そのテロリズムの根底にある思想です。その思想が正当だと思わせられるのなら、テロリストの目的が達せられる可能性があります。そうでないのなら、テロリストによる目論見は破綻する可能性が高いと言えるでしょう。
現在のテロリズムは、その正当性がかなり疑わしいものであるため、国民の連帯を強める方向に働く可能性も十分にありえると思われます。
本書の発展可能性
「地政経済学」は、地政学と経済学を総合した思考様式として提示されています。そのため、そこからの発展の可能性も考えることができると思います。
本書では、特に第3章では、今までのやり方からは奇抜とも思えるアイディアが示されています。例えば、〈政府には支出余力がいくらでもある〉とか、〈デフレの時には国民に課税する必要はない〉とか、〈「赤字財政こそが正常な状態である」〉といった考え方です。こういった考え方は、まだ浸透してはいないでしょう。浸透していくかも不透明です。
ただし、浸透したら、そこから新たな問題が生まれてくる可能性があります。これらの考え方は、政府の十分な役割を要求します。ですから、国民の政府への依存心が高まる可能性があります。つまり、国民のやる気についての問題が出てくると予想されるのです。ですから、地政学と経済学に加えて、心理学も必要になると思われるのです。経済学の心理学的な側面は、無視しえないと私には思えるのです。
お勧めです
本書の考え方は、今の世の中ではあまり理解されていないと思われます。理解しやすいものであるかと言われると、難しいようにも思えます。しかし、重要な考え方であることは間違いないでしょう。細かいところに異論はありますが、大筋として同意できます。細部について、有益なさまざまな議論も可能でしょう。
著者の緻密で誠実な探究の結果が詰め込まれています。大著であり、読むことが大変かもしれませんが、読む価値があると思います。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。







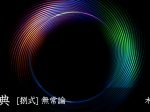



















木下様の書評を拝見し小生、中野剛志の著書『富国と強兵 地政経済学序説』をぜひ読まなければという思いがムクムクと沸いてきました。以前に同著者の数冊を読んでいましたが中でも『日本思想史新論』には国士の香りがいたしました。今回の著書は経済学、地政学の側面からのだそうですが木下さんの書評にある「心理学的な側面」ないしは哲学的な切込みを次なる展開に心待ちにしています。その際、木下様の書評も宜しくお願いします。