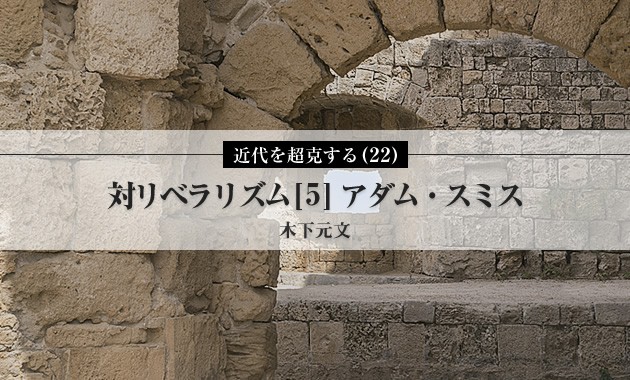
アダム・スミス(Adam Smith, 1723~1790)は、英国の経済学者で古典派経済学の創始者です。著作である『国富論』から、アダム・スミスの自由について見ていきます。
アダム・スミスの『国富論』
『国富論』では、経済における自由が語られています。
アダム・スミスは、各個人が自分自身の利益を追求して行くと、その社会にとって一番有利な資本の使い方を選ぶ結果になると述べています。このような考え方から、有名な「見えざる手」が示されます。
生産物が最大の価値をもつように産業を運営するのは、自分自身の利得のためなのである。だが、こうすることによって、かれは、他の多くの場合と同じく、この場合にも、見えざる手に導かれて、みずからは意図してもいなかった一目的を促進することになる。かれがこの目的をまったく意図していなかったということは、その社会のほうが、これを意図していた場合にくらべて、かならずしも悪いことではない。自分の利益を追求することによって、社会の利益を増進せんと思い込んでいる場合よりも、もっと有効に社会の利益を増進することがしばしばあるのである。
アダム・スミスは、この「見えざる手」の導きによって、経済における自由を唱えます。それは、特権あるいは制限を行なう制度が完全に撤廃されれば、簡明な自然的自由の制度がおのずからできあがるというものです。そこでは、各人は正義の法を侵さない限り、完全に自由にやりたいように利益を追求し、誰とでも競争することができるというのです。
そこにおいて、主権者が配慮すべき義務が三つ提示されています。
(一)自分の国を他の独立諸社会からの暴力と侵略にたいして防衛する義務
(二)社会の成員ひとりひとりを、他の成員の不正や抑圧から、
できるかぎり保護する義務、つまり、厳正な司法行政を確立する義務
(三)ある種の公共土木事業と公共施設を起こし、また維持する義務
これらの義務の根拠は、どのような個人や少人数の集団でも、そこからの利益では出費を償うことができないからだと説明されています。
アダム・スミスの検討
アダム・スミスの自由については、比較的容易に否定することができます。
自身の利益追求が、必然的に社会に有利な資本の使い方を選ぶ結果になるというのは間違いです。確かに、自身の利益追求が、社会の有利になることはありえます。しかし、自身の利益追求が、社会の不利になることも当然あります。そして、自身の利益追求によって社会が有利になる可能性が、不利になる可能性を上回る保障はないのです。
「見えざる手」の導きは、働く場合もあるし、働かない場合もあるのです。自分の利益を追求することが、社会を良くすることもあり、悪くすることもあるのです。同様に、社会の利益を増進せんとすることが、社会を良くすることもあり、悪くすることもあるのです。そしてその比率は、状況や条件によって変動するのです。ただ、それだけのことです。
また、いっさいの制度を撤去しようとすれば、新たな抑圧的な制度を生み出すか、無秩序な状態を招くかのどちらかです。当たり前の話です。公正は、様々な制度を組み合わせ、ときには制定し、ときには廃止していくという試行錯誤の中にあるのです。単に、現実の制度を次々と撤廃していくのなら、正義の法そのものが破壊されてしまいます。
また、アダム・スミスが、主権者が配慮すべき義務を三つに絞っていることについても注意が必要です。これらの三つに義務を制限すべき理由は、満足に提示されているとは言い難いでしょう。配慮すべき義務という概念は重要ですから、その数を制限せずに、柔軟に考えていくべきなのです。
ケインズの見解
蛇足かもしれませんが、ここでケインズ(John Maynard Keynes、1883~1946)の『自由放任の終焉(The End of Laissez-Faire)』を参照しておきます。ただしケインズは、アダム・スミスを自由貿易主義者と見なし、教条的な自由放任主義者ではなかったと考えていました。ですから、次の言葉はアダム・スミスに対しての批判というより、自由放任という考え方そのものに対する批判になります。この批判は、重要だと思われます。
自由放任の論拠とされてきた形而上学ないしは一般的原理は、これをことごとく一掃してしまおうではないか。個々人が、その経済活動において、長い間の慣習によって「自然的自由」を所有しているというのは本当ではない。持てるものに、あるいは取得せる者に永久の権利を授ける「契約」など一つもない。世界は、私的利害と社会的利害とがつねに一致するように天上から統治されているわけではない。世界は、現実のうえでも、両者が一致するように、この地上で管理されているわけでもない。啓発された利己心は、つねに社会全体の利益になるようにはたらくというのは、経済学原理からの正確な演繹ではない。また、利己心が一般に啓発された状態にあるというのも本当ではない。個々人は、各自別々に自分の目的を促進するために行動しているが、そのような個々人は、あまりにも無知であるか、あるいは、あまりにも無力であるために、たいてい自分自身の目的すら達成しえない状態にある。経験によれば、個々人が一つの社会単位にまとまっているときのほうが、つねに、各自別々に行動するときよりも明敏さを欠くということは証明されていない。
※第23回「近代を超克する(23)対リベラリズム[6]カントとヘーゲル」はコチラ
※本連載の一覧はコチラをご覧ください。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。







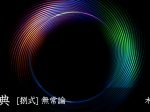



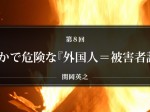















この記事へのコメントはありません。