復帰から四十二年 誰が『沖縄の心』を知っているのか
- 2015/1/8
- 政治, 歴史
- feature4, WiLL
- 4 comments
【PR】オトナのマンスリーマガジン「月刊WiLL」は年間購読がお得!
許し難いヘイトスピーチ
復帰して四十二年、本土から分離された二十七年間をも遙かに越えた。はたして、復帰とは県民にとって何だったのだろうか。
諸々の不満は、膨大な米軍基地を抱えることになったことに集約されるだろう。それは、分断国家だったことの不条理が復帰後もなお残されていることへの不満とも言えるだろう。
また、「本土の人たちの沖縄への関心の低さ」から、本土との相対化、「沖縄独立」を口にし始めたことが、新たな「沖縄問題」を生じさせているような予感がする。
昨年一月、オスプレイ配備撤回を求めるオール沖縄(四十一自治体の議会決議)の面々が東京行動の一環として銀座をデモ行進していた際、心ない一団が詰めかけて「売国奴」「琉球人は日本から出て行け」と罵声を浴びせたという。許し難いヘイトスピーチではないか。
そして昨年の五月十五日、「琉球民族独立総合研究学会」という学会が発足した。学会の会員資格は「琉球の島々に民族的ルーツを持つ琉球民族に限定」されているのでその詳細は不明であるが、この学会の特色は、研究に留まらず、琉球独立を大前提としてその実現のための研究と実践課題の遂行にあるという。
「いよいよ琉球独立論は、(居酒屋談義)を脱し、学術的論議を深めつつ、重荷を背負いながら旅立つことになる」と関係者は高ぶりを見せている。
「牙むく国」の怨念
今年の三月二十一日には「平和のための琉球自立(独立)パレード」が那覇市の国際通りであり、約六十名の参加があったという。
沖縄国際大学経済学部の友知政樹教授が現役学生を対象にした意識調査で「沖縄が独立することを考えたことがある」と答えた割合が約三割を占め、独立について賛成六%、反対四四%、分からない四九%という結果が出た。
また、ある識者は「復帰後も日本に裏切られ続け、独立論への共感さえある。独立を口にするのも悲しいが、それくらいの気概は持ちたい。独立論は、国民が国家に大事にされていないことへの異議申し立てだ」と述べ、自身のブログに「沖縄、ついにヤマトから独立へ」を書き込んだ。
四月六日のある地元紙の一面トップを見て、筆者は心臓が凍る思いがした。一段抜きの大見出しに「対沖縄牙むく国」と活字が躍っていた。辺野古ルポを記事にした社が、那覇防衛施設局長の記者会見から閉め出されたという十年も前の事実を再録した記事だった。「牙むく国」とは、最高の怨念が込められている。
地元紙の過激さはつとに定評のあるところだが、沖縄はいま、どこかで何かが変わっているという気がする。沖縄は、民族学的(シャーマン的因習)にも言語学的(ジャポニカ系)にも日本であることは、すでに明治時代に諸学者によって証明されている。ただ、生活圏の拡大過程で、遠隔地であるために遅れて日本になったという歴史があるだけである。
それが、今日に至って国家観の根元にも論が及ぶ事態が懸念される。
まさにネーション・ステーツ(国民国家)の根幹が少し軋みかけているのではなかろうか。
 この記事は月刊WiLL 2015年1月号に掲載されています。他の記事も読むにはコチラ
この記事は月刊WiLL 2015年1月号に掲載されています。他の記事も読むにはコチラ
コメント
この記事へのトラックバックはありません。


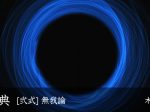


















この記事へのコメントはありません。