復帰から四十二年 誰が『沖縄の心』を知っているのか
- 2015/1/8
- 政治, 歴史
- feature4, WiLL
- 4 comments
【PR】オトナのマンスリーマガジン「月刊WiLL」は年間購読がお得!
沖縄は不条理の世界
分断国家とは、現実はどういうことになるのか。憲法をはじめ、すべての法令が沖縄には当然、適用されないということである。
当時、沖縄には憲法に代わるものとして「琉球列島の管理に関する大統領行政命令」(昭和三十二年六月)があり、その下に米国軍政府(のち「米民政府」と改称)による布令、布告、指定がこと細かく定められている。統治対象住民が少ないこともあって、本土におけるGHQよりもより遙かに直接的で、かつ強力な権力を保持し、そして執行していた。
沖縄が法律上、海外であることの端的な例は、出入国管理令上の規定である。本土の人(公務員を含め)が沖縄に渡航する場合には米民政府の許可を受け、日本政府(総理府)が発行する身分証明書(いわゆるパスポート)と入国カード、それにイエローカード(必要な予防注射をしたことを証する黄色い証明書)の三点セットが必要であった。当時、米民政府の許可、いわゆるビザが下りなくて渡航不可となった者は少なくなかった。
沖縄の法的位置が日本なのか外国なのか一見して曖昧であったことから、霞ヶ関界隈では沖縄をある時は外国、ある時は国内と見做し、省庁の独断によって対応し、政府としての一貫性を欠いていた。
たとえば大型漁船を建造する場合、国内では漁獲規制上、漁船建造にあたっては水産庁長官の「建造許可証」を必要とした。沖縄には大型の造船所がないため、本土の造船所に発注することになるが、水産庁は諸外国からの受注は認めても、沖縄の場合は水産庁長官の許可証がないことを理由(沖縄は国内だと見做し)に当初、これを拒んでいた。
また、インドネシア沖で操業中の沖縄漁船が日の丸の国旗(沖縄は国旗の使用が制限され、漁船を含む船舶は国旗の代わりに国際法上、認知されていない高等弁務官が定めた「琉球」の英字を三角型にした旗をつけていた)を掲げていたところ、インドネシア軍に「国籍不明船」として銃撃されて死亡者が出るという事件が起きた(昭和三十七年)。
この時、水産庁は沖縄漁船にはわれ関せずとして対応しなかった。外務省も施政権のないことを理由に動かなかった。このようなケースは枚挙に遑がない。まさに沖縄は「不条理」の世界だったのである。
一刻も早く祖国復帰を
筆者は、復帰の前後を通じ、公務員生活の半分を沖縄とかかわることとなった。現地に幾度となく出張しては沖縄の人たちの声を直接、聞く機会があった。また、日常的に在京の沖縄の人たちの悲痛な声を耳にした。
この不条理な世界を解消するには一刻も早い沖縄の祖国復帰が必要であり、それまでは多少、無理なことではあっても、沖縄のためになることだったら何でもやってやろうという気分で職務に対していた。
日本輸出入銀行(現在は「日本政策金融機構」に統合)は、海外に船舶やプラント等を輸出する事業を促進するため、本土の輸出企業にクレジットを与える国の金融機関である。沖縄は海外なので、同行の対象業務に含まれている。
しかし、同行の「業務方法書」では沖縄には潜在主権があるという理由で、「潜在主権地域留保」としてクレジットの金利が他の海外より高く設定されていた。このこともあって、同行の資金は沖縄向けに全く利用されていなかった。
これは不合理であると認識した筆者は「潜在主権地域留保」を撤廃すべく、同行の総裁・森永貞一郎(元大蔵省事務次官、のちの日銀総裁)に直訴することにした。このような政策変更要求は本来、ボトムアップ方式で事務的に進めるのが通例である。
しかし、同行に話を持ちかけても、途中の段階で監督官庁である大蔵省と内々に相談するなどして、色良い結果が出ることは一般的に言って無理である。
直訴とは電話で秘書を通じて総裁に直接、話し合いを申し入れるということである。森永総裁ならきっと話を聞いてくれるという確信めいたものがあった。昭和四十一年、復帰がまだ話題とならない頃のことで、筆者がまだ係長の時である。秘書からは会ってくれるという返事があり、上司の課長と一緒に早速、総裁室に伺った。
総裁は当方の言い分を無言でじっと聞いたのち、「よろしいです。しかし、個別の案件が沖縄の発展に役立つかどうかは、そちら(総理府)が判断してください」と即決された。行内の部下とも相談せずに、総裁の結論は明快だった。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。







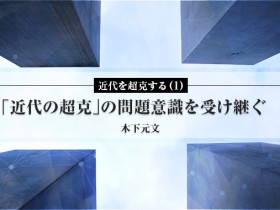













この記事へのコメントはありません。