制度を拒否する象徴としての「名前」 劇評:あやめ十八番『ゲイシャパラソル』
- 2016/7/6
- 思想, 生活
- 2,418 comments


あやめ十八番『ゲイシャパラソル』
作・演出=堀越涼
2016年5月、サンモールスタジオ
演劇ユニット・あやめ十八番の作品を初めて観た。劇場は新宿区1丁目のマンションの地下にあるサンモールスタジオ。開演前の地下の階段には、チケットを求める観客が列を成している。サンモールスタジオでこんな光景に出くわしたのは初めてだ。これだけでも、すでにこのユニットが人気になりつつあることを感じさせる。主宰の堀越涼は花組芝居に所属する俳優。花組芝居は1987年結成の、歌舞伎を下地にした作品を中心に上演する劇団(主宰・加納幸和)で、「ネオかぶき」のキャッチコピーで知られる。歌舞伎が発祥した当初にあった、大衆に広く親しまれる「娯楽」の側面。それを現代に蘇らせる活動を一貫して行っている。2006年に花組芝居に入団した堀越が、2012年に自身の作品を上演するためのユニットとして、あやめ十八番は旗揚げされた。
今回の公演は2014年初演の『江戸系 諏訪御寮』と新作『ゲイシャパラソル』の二本立て。私は『ゲイシャパラソル』を観劇した(作・演出=堀越涼)。正方形の舞台。客席は正面と下手の2方向から挟むように設置され、上手には三味線、ギター、ピアノ・パーカッションを担当する地方(じかた)が座る。彼らによる生伴奏とオリジナル劇中歌、舞台を縁取る電飾やカラフルな照明。何もない舞台を様々な場所に見せ、登場人物を手際良く裁く演出、そして弾けるところは弾けつつも、しっかりとリアリズムの演技ができる俳優たち。これら舞台上で展開される様々な要素が、古典と現代を融合した艶やかでかつつポップな舞台に仕上げていた。確かに、花組芝居由来の舞台だと納得させられる。
地方とは、踊りを担当する芸者=立方(たちかた)に伴奏や唄を付ける者のこと。そう、本作は江戸時代に花町として栄えた、深川芸者の物語である。舞台には着物姿の芸者や太鼓持ちが登場するものの、時代設定は平成60年の、スマホも登場する遠い未来。この辺の時代と風俗の絶妙な錯誤が、演劇らしい虚構を強調すると共にポップにしつらえた舞台表象にもよく合っていた。

あやめ十八番『ゲイシャパラソル』
作・演出=堀越涼
2016年5月、サンモールスタジオ
物語は、かつてトニー谷が歌った『あんたのおなまえ何アンてエの』を替え歌にした劇中歌が象徴している。具体や抽象を問わず、すべからく物には名前が付いている。人間にとってのそれは個人を識別する記号だ。名付けは親から与えられたに過ぎないのに、それが次第に意味を持ち始め、アイデンティティにすらなっていく不思議さ。本作は名前と実体を巡る問題を、恋愛関係に絡めて描かれる。
加えて、物語を駆動する名前という要素が、戸籍制度に接続されている点がミソだ。未来の日本では、中国人の「爆買い」が日本人の名前=戸籍にまで及んでいる。国力が減退した日本人が大金を手に入れるには、戸籍を売るくらいしか手段がなくなっているのだ。しかし戸籍を売って中国名になったことで社会保障を受けることができず、多くの者はやがてホームレスになるしかない。対して中国人資本家は、日本人の戸籍を買ったことによってますます日本での経済活動がしやすくなった。
深川にある柳屋の芸者たちも皆名前を売っているが、仇吉という芸者だけはかたくなに名を売ろうとしない。そのため、仇吉は「花柳界の宝」として有名だった。気が強く、客にもズバズバ物を言う仇吉が名前を売らないのは、その性格と相まって日本人としての誇りの高さが故かと思われたが、実はそうではなかった。仇吉にはそもそも戸籍がなく、売る名前がないのだ。父親は仇吉が生まれた際、値段を吊り上げるために名前を買う中国人に自らが望む名付けをしてもらおうとした。だが当の中国人は逃げた。だから出生届を出すべき14日を過ぎてしまったのだ。結果、父親は仇吉を柳屋へ売り、自らは姿を消す。
1
2コメント
この記事へのトラックバックはありません。







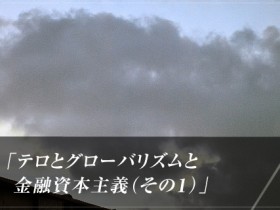













この記事へのコメントはありません。