
こんにちは、島倉原です。
失われた20年の原因を巡る諸説の妥当性について、何回かに分けて分析してきましたが、今回以降は残った「(7)金融緩和不足説」「(8)財政出動不足説」を対比しながら検討してみたいと思います((8)についてはもともと「財政支出不足説」と称していましたが、政策の選択肢に「支出拡大」だけではなく「減税」も含めるため、訂正します)。
昨今のいわゆるアベノミクスの「第1の矢(大胆な金融政策)」「第2の矢(機動的な財政政策)」は、両説に対応したものと捉えることもできます。
(なお、「(4)新興国経済成長説」には一度も言及していませんが、同説では日本だけが長期デフレに陥っていることが説明できないことを指摘しておけば十分でしょう)
金融政策と財政政策の役割
金融緩和不足説、財政出動不足説のいずれも、「金融緩和や財政出動といったマクロ経済政策によって、需要(支出意欲)の拡大が促され、経済活動が活性化する(失業率が低下し、国民全体の所得が拡大する)」ことを前提としています。これは「日本経済長期低迷の原因が『供給』よりもむしろ『需要』にある」という、本連載でも何度か指摘した現実とも合致しています。
それぞれの政策手段、及び想定される効果(実際にそうなるかどうかは別として、当該手段を正当化する理屈)についてまとめたのが表1です。
【表1:金融緩和/財政出動における政策手段と想定される効果】
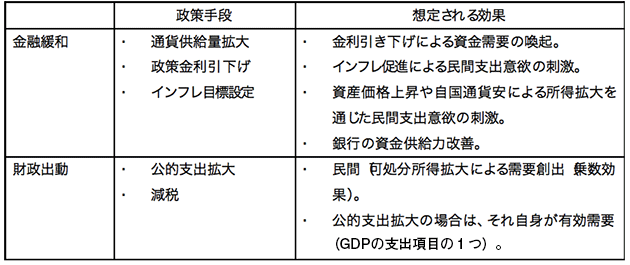
例えば、設備投資や住宅購入を行う際、企業や家計は必要な資金の一部または全部を銀行から借り入れます。その際借入金利が低ければその分だけ返済金総額は減少するため、企業や家計にとっての負担は軽減します。その点に着目して「金利を引き下げれば負担感が減少した分、設備投資や住宅購入をしようとする主体が増え、経済全体の需要が拡大するだろう」と期待しているのが「政策金利引き下げ」です。
なお、「金融緩和」に掲げた政策手段は「財政出動」に掲げたそれと異なり、それぞれが必ずしも独立したものではありません。政策金利やインフレ率を目標水準に保つ、あるいは到達させる具体的手段は大概「通貨供給量拡大」を伴います(その意味では、政策手段の欄を「通貨供給量拡大」に一本化してもあながち間違いではないでしょう)。
これらの政策手段、「需要喚起との直接的な結びつき」という観点では、「公的支出拡大>減税>金融緩和」の順で強くなっています。
すなわち、公的支出の拡大が「それ自身が経済の一部門である政府の需要行為であることに加え、他の誰か、即ち民間部門の所得(支出の原資で、かつ返済不要)を直接増やす(誰かの支出は別の誰かの所得である)ことによって、プラスアルファの需要喚起も見込める」行為なのに対し、金融緩和の効果は間接的か、せいぜい「返済その他の見返りが必要な支出の原資」である「金融」の環境を改善するものでしかないからです。
このことと、本連載の初回「積極財政論の出発点」でも示した各政策変数とGDPとの長期的な関係(図1)を踏まえて素直に考えれば、それだけで「財政出動こそが必要かつ最も効果的な経済政策」という結論が出てきても良さそうなものですが、世間の主だった論調がそうなっていないのは、ご存じの通りです。
【図1:日本の各種マクロ経済指標の推移】
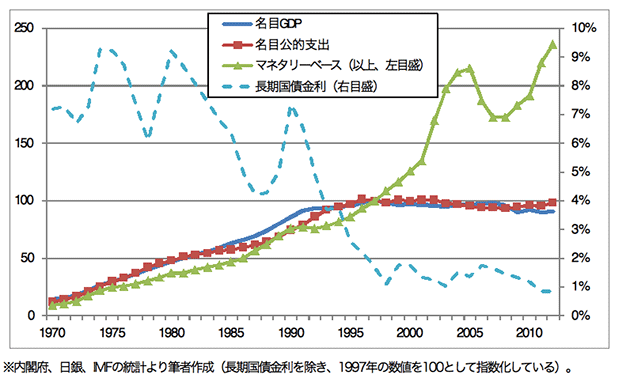
両説の原点は1930年代の世界恐慌
金融緩和不足説の源流であるマネタリズム、財政出動不足説の源流であるケインズ経済学のいずれも、1929年のニューヨーク株式市場暴落に端を発する歴史的事件「世界恐慌」(米国に限れば「大恐慌」)に対する研究や洞察に端を発しています(米国の中央銀行であるFRBのバーナンキ議長は「大恐慌の権威」として有名です)。
また、岩田規久男・日本銀行副総裁を筆頭とする、いわゆる「リフレ派」として名をはせている方々の多くは、同時期の日本の恐慌(昭和恐慌)を研究対象とした「昭和恐慌研究会」のメンバーです。
次回以降は、同時期の経済状況と日本の現状を照らし合わせながら、各説の妥当性を検証してみたいと思います。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。



























この記事へのコメントはありません。