経済社会学のすゝめ
- 2014/8/6
- 経済
- アダム・スミス, ケインズ, シュンペーター
- 113 comments
道徳心こそ利己心の御者
経済学の始祖と言われる古典派経済学者のアダム・スミスは、「個人の利己的行動が社会全体の厚生につながる」というヴィジョンの下、現代における市場メカニズムの原型を提示した人ですが、彼の学説の中に経済と社会(非経済領域)の「ゆるやかな交渉形態」を見て取ることができます。実際、スミスは利己心に基づく自由な経済活動に対し、「道徳」という社会的規範を制約条件として課していたのです。すなわち、全ての利己的な行動が許容されるのではなく、各人の道徳心というフィルターを通して選別されなければならないと考えていたのです。
そのフィルターこそ、スミスの言葉を用いるなら、「シンパシー(sympathy)」なのです。それは「共感」とか「同感」と訳されています。利己的な行動をする前に、「それが果たして他者の共感を得られる行動であろうか」を判断せよということです。共感が得られないと思われるのであれば、やってはならないのです。共感を得られる行動とは、社会の大多数に認められた行動です。その社会の存続のために歴史的に培われた慣習、文化、伝統に基づく取り決めです。経済行動はそれに従わなければならない。利己的目標の追求のために、騙したり、盗んだり、脅したりしてはならないのです。
しかし、客観から主観への価値概念の転換によって、経済学の主流は新古典派になりました。スミスのヴィジョンはワルラスによる一般均衡論へと精緻化されましたが、その過程で、先述した如く、現実的諸要因は夾雑物として理論から排除されました。もちろん、捨てられた中に道徳も含まれていましたので、スミスの経済と社会のゆるやかな連関の想定も忘却の彼方に追いやられました。
スミスの考え方から導かれることは、「経済と社会の相互交渉を論じるためには、人間の経済行動が、経済的動機だけではなく他の社会的動機にも依存する」と定式化することです。「理念型」として考えるということです。人間は、底なしの我欲のためにのみ経済行動をするのではないのです。もちろん、そういう動機で行動する人もいるでしょう。しかし、全員ではない。損得は二の次で、好きな仕事だから働いている人がいる。子供の将来を思って働いている人がいる。神の栄光のために働くプロテスタントの人もいるでしょう。様々な動機で経済活動を行なっていると考えるのが自然なのです。であるならば、新古典派のように同質的主体から成る経済社会を想定するのではなく、異なる価値観を有する異質的主体の集合として経済社会を捉える方が、現実的であることは明らかでしょう。
ミクロ理論はひとつではない
問題は経済分析にそうした想定を如何に導入するかということです。経済行動が経済的動機と共に、他の社会的動機からも影響を被るとすれば、もはや新古典派のミクロ理論を現実分析の土台とすることは不可能です。別のミクロ理論、例えば「(社会)包括的ミクロ理論」が必要になってくる。包括的ミクロ理論に立脚するなら、新古典派ミクロ理論は経済領域の中で閉じられた「特殊なミクロ理論」として学問的に位置づけられることになります。新古典派ミクロ理論が経済学における唯一のミクロ理論と考えてはなりません。それは、部分理論に過ぎないのです。しかし、未だ包括的ミクロ理論は構築されていないわけです。その場合、どうしたらよいのでしょう。
実は新古典派ミクロ理論は、それ自体、一つの理論的構築物として経済学の中に存在している限り、全く問題を生じさせるものではありません。「そのように仮定すれば、そうなりますね」という程度の経済トピックスに過ぎないのです。誰もそれを現実の姿だと思ってもいないわけですから。
ところが、「その姿こそ現実だ」と強弁する経済論理が主流となってしまいました。ミクロ理論と現実を合体させる論理が、いわゆる「マクロ経済学のミクロ的基礎づけ」です。それはマクロの経済現象の説明をすべてミクロ主体の行動から説明する論理構造となっているため、結果的に現実経済をミクロ理論の鋳型に押し込むことになりました。同質的主体から成る市場システムへ無理やり押し込むのです。当然、鋳型が小さすぎて、入りきらない。異質性の存在という現実経済の真理など全く入らない。
さらに悪いことに、主流派経済学の論理が経済学界だけに留まらず、エコノミストを通じて財界、政界、官界、マスコミ界へも浸透し、実際の経済政策の理屈として濫用される事態が生じてしまいました。事ここに至らば、主流派経済学の伸長を、経済学界における机上の空論の隆盛と等閑視することはできなくなりました。主流派の論理を批判すると同時に、それに代わるべき経済理論の構築が急がれる所以であります。そうしなければ、現実経済は荒唐無稽な論理に振り回されることになってしまいます。実際、「失われた20年」はその象徴なのです。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。







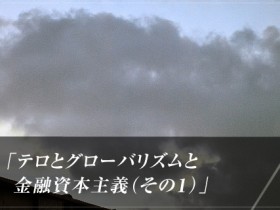













興味深い論考をありがとうございます。何点か気になった点があり、さらにご説明いただければ幸いです。
1.「主流派経済学は人間を社会的存在と見なさない」の項は基本的に間違っていると思いました。効用関数に入っているものはすべて交換可能でなければならない、というのは正しい指摘だと思いますが、物欲以外の社会的な活動から得られる満足が交換(=比較)可能でないと考えるのは誤りではないでしょうか。実際、その後の部分で、筆者自身が「子どもの入学式から得られる満足」と「ステーキを食べる満足」を比較しています。主観的に交換可能であれば限界代替率は計算可能であり、理論上は、社会的活動からくる満足であっても、それを効用関数に含めて新古典派経済学の枠組みで説明することは可能ではないでしょうか。また、論考中の入学式とステーキの例で言えば、まず入学式から得られる満足とステーキ1枚から得られる満足が等しいという(非現実的な)仮定から出発すれば、ステーキ2枚から得られる効用が入学式から得られる効用よりも大きいという(非現実的な)結論を得ても何ら不自然ではないと思います。そもそも、現実の経済ではステーキ1枚から得られる効用は子供の入学式から得られる効用と比較にならないほど小さいというのが現実的な仮定であって、ステーキ2枚の効用が入学式の効用を上回るなどということはまずあり得ないだろうと思います。筆者は、非現実的な仮定から導かれた帰結の妥当性を、現実に照らして判断している点で、インプリケーションの導き方、解釈の導き方に無理があると思います。こうして考えると、新古典派経済学では物欲の充足が唯一の価値観ということ自体が新古典派経済学の価格理論に対する誤った理解に基づいていると思いますが、いかがでしょうか。
2.シュンペータとケインズの統合に関する項で展開されている主張は、2009年に出版された吉川洋『いまこそ、ケインズとシュンペータ―に学べ―有効需要とイノベーションの経済学』と非常に似通っていますが、この項は本書を参照したのでしょうか?そうであれば、その旨明記すべきと思いますが、いかがでしょうか?