村上春樹における文学と政治 ―デタッチメントとコミットメント
- 2014/12/9
- 社会
- 31 comments
【オウム真理教事件が与えた衝撃】
60年代の世界を支配した大きなパラダイムはやがて90年代から21世紀にかけて崩れていく。ソ連は崩壊し、冷戦は終結した。国際金融資本の強欲が国境の壁を越え世界をかけめぐっている。インターネットの爆発的普及は国境など一顧だにせず、情報は瞬時に世界の隅々に行き渡る。誰もがその発信者になり得る時代だ。
右翼の大物の中に入り込んで強大な権力機構を操った「羊」は、この大物を使い捨てにして「鼠」の中に住みついた。「鼠」はその「羊」を殺すために、隙をついて自ら命を絶った。
村上春樹は1978年の時点で、60年代を支配した巨大な壁の崩壊とその後の時代の到来を、優れた作家の直感で予見していたのであろう。「鼠」の中に入り込んだ「羊」は、新たに到来する時代の捉えどころのない「悪」のメタファーである。
ジョージ・オーウェルの近未来小説『1984年』(1949年)は、スターリニズム下の社会を寓話化した物語で、独裁者ビッグ・ブラザーとそれに操られる人々が描かれている。
巨大な壁が崩れ、ビッグ・ブラザーが不在となった90年代以降、世界を語る大きな物語を失った人々は、雨後の筍のように跋扈する種々の物語に自らのアイデンティティを託そうとする。
そのひとつがオウム真理教に集う人々だった。1983年創設のヨーガ道場がオウムの会に衣替えをしたのが1984年で、地下鉄サリン事件の勃発が1995年である。ビッグ・ブラザー亡き後の「悪」に関心を向けていた村上春樹にとって、これは衝撃的な事件であった。
地下鉄サリン事件の被害者や遺族の証言を集めた大著『アンダーグラウンド』を1997年に発表した村上春樹は、引き続きオウム信者や元信者へのインタビューを行ない、それを『約束された場所で』(1998年)の1冊にまとめた。
この書に収められた河合隼雄との対談(1997年)で村上春樹は語っている。
悪というのは、僕にとってひとつの大きなモチーフでもあるんです。僕は昔から自分の小説の中で、悪というもののかたちを書きたいと思っていました。でもうまくしぼりこんでいくことができないんです。悪の一面については書けるんです。たとえば汚れとか、暴力とか、嘘とか。でも悪の全体像ということになると、その姿をとらえることができない。
オウム真理教事件と阪神淡路大震災(1995年)を契機として、村上春樹は社会へのコミットメントの姿勢を俄然強めていくことになる。
そして、この像を結ぶことが困難な「悪というもののかたちを模索し続けて結実したのが大作『1Q84』(BOOK1・2は2009年、BOOK3は10年)である。
【遍在する壁】
『1Q84』BOOK1第18章のタイトルは「もうビッグ・ブラザーの出てくる幕はない」である。そこで村上春樹が提起している概念が「リトル・ピープル」あるいは「リトル・ピープル的なるもの」である。ビッグ・ブラザーを喪い不安に怯える現代人が生み出す「システム」の精神にしのびよって来るのがリトル・ピープルである。目には見えない存在である。
『1Q84』はカルト教団「さきがけ」及びそのリーダーと闘うヒーローとヒロインの物語である。当初農業コミューンとして活動していた「さきがけ」が急激にカルト教団に方向転換するにあたって、リトル・ピープルが何らかの役割を果たしたとされている。
このリトル・ピープルは、大きな壁が崩れた後、世界のパラダイムが溶解しつつある中で、様々な場所で発生する小さな壁のメタファーである。
壁を一貫して作品のモチーフとしてきた村上春樹は、冒頭で触れたベルリンでのスピーチで壁の例を列挙している。
壁は私たちを守ることもある。しかし私たちを守るためには、他者を排除しなければならない。それが壁の論理です。壁はやがて、ほかの仕組みの論理を受け入れない固定化したシステムとなります。時には暴力を伴って。
世界には民族、宗教、不寛容、原理主義、強欲や不安など様々な壁があります。
【グローバリズムとナショナリズム】
村上春樹が列挙している壁の例は、冷戦終結後のアメリカ一極支配体制もやがて揺らぎ始め、世界の無極化が進行している21世紀に顕在化してきた壁である。しかしグローバリゼイションの波が広まり、国境の壁が低くなっているかのように見える現在も、依然として国家は大きな存在である。
村上春樹のスピーチになぞらえて言えば、「国家は私たちを守ることもある」となるのだが、近代の国民国家は、暴力と略奪が横溢した暗黒の中世を経て、私たちの生命と財産を守るためにこそ誕生したのだ。主権国家の原型は、ヨーロッパで長い宗教戦争を経て締結したウエストファリア条約(1648年)にあり、それは基本的に現代の国民国家体制に持続されている。
この国民国家体制を崩そうとする潮流は、ひとつはグローバリゼイションの流れであり、ふたつには近代国民国家観とは異質の中華思想を持ち、力に応じて既定の国境線を崩そうとしている中国の勃興である。さらには西洋によって定められた国境線を否定し、且つ西洋文明を武力によって否定しようとしているイスラム勢力の拡大もあげられよう。
なかんずくグローバリズムの拡大である。それは国際金融資本主義のあくなき利益追求の精神がもたらす政治行動である。国際金融資本は強欲をほしいままに振り回し、地球を国境のないひとつの世界にしようと目論んでいる。目的のためには容赦なく戦争の罠も仕掛けられる。莫大な利益が彼らに吸い上げられると同時に、国民経済は破壊され、貧富の差が著しく拡大する。
グローバリズムの敵は、国の独立を保とうとするナショナリズムである。今グローバリストがターゲットにおいているのは、ロシアの母なる大地を守ろうとしているプーチン大統領だろう。ウクライナのオレンジ革命(2004年)以降今日に至る危機的状況は、元駐ウクライナ大使の馬渕睦夫がしばしば指摘しているように、国際金融資本に率いられた勢力がプーチンを失脚に追い込むために謀っている策略だという視点から見ると、腑に落ちることがいろいろある。日本では、自由を追求する欧米と強権国家ロシアとの争いだなどという怠惰な理解が流行っているようだが。
日本人のうちの少なからぬ人たちは、グローバリズムの趨勢が日本にも到来し、国境の壁が低くなっていくと素晴らしい世界が広がるのだと思っている。サムスングループ等の大企業が外資の支配下に置かれ、利益が吸い上げられ、国民経済が破壊され、国民は収奪されるだけの存在に貶められている韓国の現状を知らないのだろうか。
村上春樹はベルリンでのスピーチで、「壁のない世界をあきらめずに想像し、求め続ける」ことの大切さを訴えている。一知半解でスピーチの言葉尻だけを聞く者は、国境の壁をなくすことに大いに共感し、その大群がグローバリストたちの活動の肥やしになるというわけだ。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。







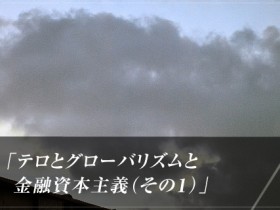











〔訂正〕
p.5【オウム真理教事件が与えた衝撃】の章で上から7行目に「1978年の時点で」とありますが、正しくは「1982年の時点で」です。筆者の誤記です。訂正します。