
北海道大学の学生はなぜ「イスラム国」に志願したか
これから述べることは、一部の新聞、公共放送、ウィキペディアその他ネット情報から得たごく限られた知識に基づいていますので、「こうこうである」という断定ができません。そのため、「かもしれない」とか「ではないだろうか」とか「ように思われる」とか「だろう」といったあいまいな表現がところどころにあります。現時点(2014年10月31日)における判断ですから、今後の情勢次第で変更される余地があることをあらかじめお断りしておきます。
言論人として責任逃れではないかと思われる向きもあろうかと予想されますが、そうではなく、私自身は、以下の問題について、認識の不確実性と限界とを認めたうえで、なお今の時点で自分の考えを公開しておく必要を感じるという、それなりに誠実な態度だと思っています。
2014年10月6日、北海道大学の学生(26)が「イスラム国」に加わろうとしたとして、警察庁が事情聴取をしました。これには、元同志社大学教授でイスラム教研究者の中田考(なかた・こう)氏が紹介・斡旋の役割を果たしたと報じられています。ちなみにこの中田氏という人は、私が捉ええた限りでは、かなりまともで優秀な学者であるのみならず、一定の思想的な信念をもって、しかも柔軟な姿勢で行動している人のように思われます。
報道する側は私たちの抱く印象をコントロールする
この事件の報道のされ方、問題の仕方について、私は有力メディアに対してある疑問を禁じえませんでした。それは、当の「イスラム国」がどういう歴史的・社会的・宗教的な背景のもとにこれほど急激に勃興しつつあるのかという客観的な分析抜きに、ただなんとなくタリバンやアルカーイダとつながる過激なテロ組織というイメージを前提にして語られていたからです。
この前提だけに従うと、ただちに、この学生はカルト宗教に入信するのと同じような「誤った信念」に取りつかれて「イスラム国」に加わろうとしたのだという判断が成立します。
じっさい、たとえば10月27日のNHKラジオの夕方番組では、当の「イスラム国」が世界に向けてインターネットを駆使し、兵士として参加するように巧妙な勧誘を行っている事実を報じたあと、オウム真理教との類推で、現代日本の一部の若者がなぜこのような「過激な」集団に参加しようとするのか、その個人心理的な背景は何かといった問題意識に終始した解説がなされていました。いわく、就職が思うようにいかない不満、性的な不満、日本社会の将来に対する絶望感、等々。
たしかに、参加する個人の心理としては、そのような不満や絶望感が動機となっている面があるのかもしれません。そういう側面からこの現象を追いかけるアングルは一定程度必要なものでしょう。ただ、私はこういうやり方に特化するその報道姿勢に対して大いに不満を感じるのです。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。







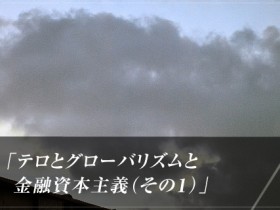












かなり納得しました。
触れられていない点について私なりの推定をさせて頂くと、イラク戦争のあとの米国企業の利権を巡る横暴な振る舞い、オスロ合意の後のイスラエルのパレスチナに対する振る舞い、これらがイスラム教徒の怒りに火をつけたのだと思えてなりません。
ナオミ・クラインの「ショック・ドクトリン」には、イラク戦争の後の米国企業のあまりのひどさが、痛烈に批判されています。せめてイラク戦争の事後処理に米国企業が割り込むことなく人道的に行われればここまでの事態にはならなかったのではないでしょうか。
イスラム国のことは詳しくない私ですが、非情に興味があります。