ポーランド現代史の闇
- 2015/6/5
- 歴史
- feature4, WiLL
- 10,900 comments
感銘したサック氏の言葉
戦後ポーランドの歴史を巡る問題をさらに複雑にしているのは、ポーランド人が行ったユダヤ人迫害の問題である。この問題は本稿の主たるテーマではないので深入りはしないが、第二次世界大戦中、ドイツ占領下のポーランドでは、ポーランド人によるユダヤ人迫害が頻発していた。
有名な事例としては、ポーランド東部のイェドバブネ村で、多くのユダヤ人がポーランド人によって惨殺された事件などがあるが、これは日本でも、新聞やNHKによって大きく取り上げられたので知っている人も多いだろう。そして、戦後長い間、共産主義政権下のポーランド人たちは、それを「ドイツの仕業」にしていたというのである。
戦後、共産主義政権が支配したポーランドでは、こうした戦時下のポーランドで起きたポーランド人によるユダヤ人迫害はタブー化され、ポーランドの民主化が進んだ二〇〇〇年頃まではほとんど語られなかった。
こうした大戦中のポーランドの状況が、ポーランドのユダヤ人たちを異常な心理に駆り立ててしまったことは明らかである。ポーランドに残留したドイツ民間人への迫害の問題を考えるうえで、当時のユダヤ人が置かれた状況とそのなかでの異常な心理を忘れて論じることはできないだろう。
前述のように、私がサック氏のこの本に出会ったのは一九九〇年代半ばのことである。その内容に私は衝撃を受けた。同時に、この本のある個所に深い感動を受けた。それは、サック氏がこの本の前書きに書いた次のような言葉である。
〈私は、一九四五年に彼ら(ユダヤ人)が大勢のドイツ人を殺したことを知ってしまった。ナチスたちではない。ヒトラーの手下たちでもない。ドイツの民間人である。ドイツの男性、ドイツの女性、子供たち、赤ん坊たちである。その人たちの罪は、ただドイツ人であることだけであった。
いかにユダヤ人たちの怒りが理解しうるものであったとしても、ドイツ人たちはドレスデンにおいてよりも、あるいは広島における日本人よりも、真珠湾におけるアメリカ人よりも、英国本土の戦いにおけるイギリス人よりも、あるいはポーランドのポグロム(ユダヤ人迫害)でのユダヤ人自身よりも、多くの民間人を失ったのである。
私はそれを知り、そしてさらに知りたいと切望した。(中略)私は聖書学者ではないが、土曜学校に通った。(中略)そして私は、トーラ(ユダヤ教の聖典)が私たちに正直な証人であることを命じていることを、つまり誰かが罪を犯したことを知りながらそれを報告しなかったら私たちも罪を犯すことになる、と述べていることを知っている〉〈私はヨーロッパで調査を進める一人のユダヤ人として、もしユダヤ人が何らかの道徳的権威を守ろうと思うならば、ユダヤ人の司令官たちが何をしたかを報告する義務があると感じたのである。
私はもしかしたら、一部のユダヤ人たちが私に向かって、「どうしてユダヤ人なのにこんな本を書けるのだ?」と尋ねるかもしれないと想像した。そしてその問いに対する私の答えは、「いや、なぜユダヤ人がそれを書かずにいられるのだ?」以外にはないことも、私はわかっていた〉(ジョン・サック著、『目には目を』前書き十~十一ページより。西岡訳)
サック氏のこの言葉を読んだ時の感動は忘れることができない。サック氏は、敬虔なユダヤ教の教育を受けたユダヤ人である。だからこそ、サック氏はこの問題を調査し、発表したのである。サック氏のこの言葉を読んだ時、私はユダヤ人とユダヤ教の偉大さに触れた気がした。
そしてサック氏のこの言葉に、「一民族だけの神」という思想に反発して、ユダヤ教会から破門されたオランダのユダヤ人哲学者、スピノザの面影を見た気がした。いかなる民族も国家も道徳的に完全ではあり得ない。問題はその民族、国家のなかでそのことを直視する個人がいるかいないか、ではないだろうか。ユダヤ人のなかにはいたのである。
ポーランド女性が見たもの
冒頭で紹介したポーランド人女性に話を戻そう。私はその女性に、「ポーランドにドイツ人はいるの?」と訊いただけである。
ところが、私のその質問に彼女は何も答えず、全身を震わせ始めたのであった。彼女の怯え方は、繰り返して言うが、私がこれまでの五十八年間の人生で目撃したことがないほどの怯え方だった。
それは、一九八〇年代はじめのことである。当時、私はここに書いたようなポーランド現代史の闇の部分を全く知らなかった。
そして昨年、私はある雑誌の記事を見て、その遠い昔の不可解な出来事の意味が何であったのかをついに理解できた気がした。
その記事は、ドイツの週刊誌『デア・シュピーゲル』に載ったある記事である(二〇一四年四月七日号)。「魂の親族たち」と題されたその記事は、ウクライナ情勢が緊張するなかで、同誌が第二次世界大戦後、ウクライナや東欧に残留させられたドイツ人たちについて特集した記事であった。そのなかに、戦後ポーランドのある都市に作られたドイツ人収容所に関する記述があった。
そして、その都市にあった収容所で、戦後長い間、抑留されていたドイツ人の逸話が紹介されていた。──その都市こそ、あのポーランド人女性が育った町なのであった。
ここで先ほど引用したイアン・ブルマ氏の著作の一節をもう一度、引用しよう。
〈ドイツ人に対する暴力の最悪の事例が、民兵によって犯されたのは疑いない。彼らは強制収容所を運営し、収容者を拷問、無作為に殺し、人びとをさらし台にかけたが、時には何の理由もなくそうした〉
そうしたドイツ人たちは、ポーランド人の前にしばしばさらし物にされた、とブルマ氏は書いている。私が出会ったその女性は戦後生まれのポーランド人であったが、彼女が育った町にはドイツ人の収容所があった。子供の頃、彼女は何を見たのだろうか。
戦後七十年の時が流れ、歴史はなお政治の道具として利用され続けている。それは、ある意味では仕方のないことかもしれない。だが私自身は、歴史を政治の道具としては語りたくない。
真の和解を遂げるために
私は、歴史が政治や外交の題材としてではなく、悲惨な歴史のなかで命を落としていった人々の運命に思いを馳せ、生きている私たちが真の和解を遂げるための礎として語られることを願うのである。
あの戦争で、一体どれだけ多くの子供たちが親を失い、兄妹・姉妹を失い、そして自らの命を落としていったのだろうか。それこそが、私が一番知りたいことである。ユダヤ人もドイツ人もない。子供たちである。そして、戦後もそうした悲劇の残滓に対峙して、幼い心を傷つけられた子供たちがどれだけいたことだろうか。
この記事を、ポーランドとその他のあらゆる土地で、第二次世界大戦中と大戦後に命を落とした全ての子供たちに捧げる。
 この記事は月刊WiLL 2015年6月号に掲載されています。他の記事も読むにはコチラ
この記事は月刊WiLL 2015年6月号に掲載されています。他の記事も読むにはコチラ
コメント
この記事へのトラックバックはありません。







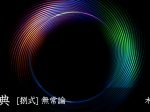















この記事へのコメントはありません。