笑えない悲喜劇 劇評:東京デスロック『亡国の三人姉妹』
- 2016/11/25
- 思想, 生活
- 30 comments


photo by bozzo
東京デスロックが『かもめ』に続いて、チェーホフの『三人姉妹』を多田淳之介の構成・演出で上演した。『가모메 カルメギ』と題した『かもめ』は、韓国のDoosan Art Centerと第12言語演劇スタジオとの共同制作。2013年にソウルで上演された後、2014年に日本で上演された(KAAT 神奈川芸術劇場 中スタジオ)。舞台を19世紀末のロシアから1930年代の朝鮮に置き換え、女優に憧れるニーナを韓国人、ニーナをたぶらかす作家・トリゴーリンを日本人俳優が演じた。ニーナとトリゴーリンの関係に、朝鮮を統治した日本という支配・被支配の構図を浮かび上がらせる演出であった。
本サイトでは、3月に上演された『Peace (at any cost)?』の劇評を執筆している(http://asread.info/archives/3248)。そこでも記したように、多田作品の特徴は、時に客席をも含めた空間造形によって、作品テーマそのものを視覚的に取り出す。作品で問われている事柄を、観客がより肉感的に知覚できるようにという演出意図がある。本作は舞台と客席が明確に分断された空間ではある。とはいえ、チェーホフ作品に漂う、多焦点的でつかみどころのない脱中心化された物語というエッセンスを抽出しながら、今日に上演する意義を付け加える演出が施されていた。近年の多田作品から看取される、真面目さに裏打ちされた作品造形によって、100年以上の時が経っても色あせないチェーホフの作品が浮かび上がってきたのである。
タイトルに「亡国の」と付いている通り、生まれ故郷のモスクワへ帰ることを希望しながら、父の死後に片田舎で暮らしている三人姉妹とその家族を、亡命者・難民として描いている。『三人姉妹』から抉り出した最大のエッセンスはここにある。彼女たちが、ヨーロッパ入りを目指して移動するシリアを始めとした中東やアフリカ難民、あるいはイスラエル建国後に周辺国へ逃れて、故郷へ帰ることを切望するパレスチナ難民になぞらえられていることは明らかだ。
そのことを視覚的に一発で了解させるように、舞台空間には難民キャンプを思わせる大きなテントが置かれている。その前には布団がいくつか広げられており、そして地球儀やおもちゃといった数々の玩具で溢れている。舞台の上手と下手には、数多くのダンボールが積み重なって配置されている。それらのあらゆる道具に、無数の丸い穴が開いているのだ。それは登場人物が身に着けた衣装にも及んでいる。これが意味するのは、物事の中身に芯がなく、空っぽであるということ。劇中、回転しながら放たれるミラーボールの無数の光も丸い。それが劇場空間の壁に投影された時、からっぽなのは物や人だけでなく、世界そのものであることが突きつけられる。
そのからっぽさをさらに強調するのが、俳優の演技である。手で持った人形などを使って発語したり、相手がいる会話の台詞を独り言のように俳優が発語するシーンがたびたび訪れる。また役柄も固定されてはいない。次女・マーシャが亡き父と故郷モスクワを重ねて恋をする、砲兵隊長のヴェルシーニンが登場しない。他の役柄の俳優が戯曲を片手に彼の台詞を読むことで処理するのだ。『三人姉妹』で重要な登場人物であるヴェルシーニンが不在であることによって、対人関係における会話が成立しない。モスクワへの帰郷という姉妹の願いが対象を失って空転しており、はじめから叶わないことが示されているのである。このように、俳優の演技は観客に感情移入をさせないように、非リアリズム的で熱度が低い。まるで銃弾で撃たれたように蜂の巣になった舞台空間。そして、相手が不在でズレて噛み合わない会話や、内容のない台詞を独り言のようにとつとつと語る俳優。これらが、半死半生の空虚さを抱えるチェーホフ劇のエッセンスを捉えているのである。
1
2コメント
この記事へのトラックバックはありません。





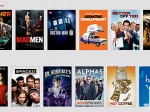

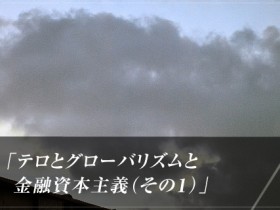












この記事へのコメントはありません。